神経生物学と眼科学のスタンフォード大学教授であるアンドリュー・フーバーマンが、科学と日常生活に役立つツールについて議論します。本エピソードでは、「断食(ファスティング)」、または「時間制限食(タイムリミテッド・イーティング、TRE)」に焦点を当てます。睡眠中に誰もが断食しているため、特定の食事スケジュールが、脂肪減少、筋肉の維持、臓器の健康(肝臓、腸)、遺伝子、炎症、回復、運動能力、認知、気分、そして寿命にどう影響するかを探ります。これは、身体と脳のシステムをよりコントロールするための深い理解をもたらします。
参考
血糖値と死亡率:重要な示唆
「Cell Metabolism」に掲載された研究では、安静時の血糖値が高いほど人間の死亡率と関連があることが示されました。加齢とともに血糖値は上昇する傾向にあります。興味深いのは、マウスでの結果とは正反対であったことです(マウスでは低血糖値が死亡率と関連)。この知見は、動物実験の知見を人間に適用する際の注意点の重要性を示しています。
食事の「タイミング」の重要性
本エピソードの核心は、「何を食べるか」と同じくらい「いつ食べるか」が、特に肝臓と精神の健康において重要であるという点です。食事をすると血糖値とインスリン値が上昇し、食事をしないと低下します。摂取する食品の種類によって上昇度合いは異なります(単純糖質 > 複合糖質 > 食物繊維 > タンパク質 > 脂肪)。身体が真の「空腹状態」に移行するには、最後の食事から約5〜6時間かかります。
サッチン・パンダ氏の画期的な研究と体内時計
時間制限食のパイオニア、サッチン・パンダ教授(ソーク研究所)による2012年のマウス研究は、この分野の基礎を築きました。この研究では、同じ高脂肪食を好きなだけ与えられたマウスが肥満で病気になるのに対し、高脂肪食を1日8時間の制限された時間帯にのみ摂取したマウスは、体重を維持・減少し、健康が改善されました。この8時間枠は、研究室の現実的制約から生まれたもので、絶対的な「聖なる」時間ではない点に注意が必要です。
時間制限食の重要な効果は、身体の「体内時計(サーカディアンリズム)」を整えることにあります。体と脳の遺伝子の約80%が24時間周期で活動しており、このリズムが適切に保たれると健康が増進されます。光が主要な時間調整因子ですが、食事のタイミングも強力な調整因子です。活動期(人間は昼間)に食事を制限することで、体内時計遺伝子の発現が規則的になり、多くの健康効果が得られます。夜間の食事は健康に有害であるとされています。 また、肝臓の健康改善も示されており、食事時間を制限することで、炎症性マーカーの増加を抑制し、褐色脂肪(代謝を高める健康な脂肪)を増やし、血糖調節を改善します。
理想的な時間制限食のスケジュール
実践的なスケジュール設定のルールは以下の通りです。
- 起床後、少なくとも1時間は何も食べない。
- 就寝前の2~3時間は、食べ物や液体カロリーを摂取しない。 睡眠中の断食は、細胞修復(オートファジー)や脳の老廃物除去に特に重要です。
食事時間の「理想的な」配置は、睡眠中の断食を最大限に延長することです。客観的に見て最も健康に良いのは日中の真ん中(例:正午~午後6時)ですが、社会的適合性が低いです。現実的なスケジュールとして、午前10時~正午頃に食事を開始し、午後6時~8時に終了するパターンが推奨されます。これにより、就寝前のバッファを確保しつつ、社会生活との両立が可能です。 ほとんどの人は自分の食事時間を長めに設定してしまう傾向があるため、例えば8時間目標であれば6~7時間、10時間目標であれば8~9時間を目安にすると良いでしょう。 さらに、食事時間の「一貫性」も極めて重要です。週末などに食事時間が大きくずれると、体内時計に「時差ぼけ」を引き起こし、健康効果を相殺する可能性があります。
空腹状態への移行を促進する戦略
最後の食事を終えても、身体が完全に空腹状態になるまでには時間がかかります。この移行を早める戦略として:
- 食後の軽いウォーキング(20~30分)は血糖値のクリアリングを促進します。
- 夕方の高強度インターバルトレーニング(HIIT)も血糖値を下げ、空腹状態への移行を早めます。
- グルコース処理剤として、メトホルミンやベルベリン(市販)があります。これらは血糖値を下げますが、低血糖のリスクもあるため慎重な使用が必要です。
- 塩分(電解質)の摂取は、低血糖によるふらつきや空腹感を和らげるのに役立ちます。特にカフェイン摂取時は、水分とナトリウムが排出されやすいため推奨されます。
細胞・ホルモンへの影響と特定の考慮事項
空腹状態は、細胞の成長を抑え、修復と老廃物除去(オートファジー)を促進します。時間制限食は、腸内マイクロバイオームの健康を改善し、非アルコール性脂肪肝疾患の予防・改善にも寄与します。また、褐色脂肪の貯蔵量を増やすことも示唆されています。
ホルモン面では、サイクリストの研究で、時間制限食が遊離テストステロンを有意に減少させる可能性が示唆されましたが、ストレスホルモンであるコルチゾールも減少していました。 筋肉の維持や増強を重視する場合、日中の早い時間にタンパク質を摂取することが有益である可能性があります。精神的・肉体的にストレスが多い場合や、激しいトレーニングを行っている人は、8時間より短い食事時間を設定すると、炎症や性ホルモンの問題を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。生殖能力にも影響があるため、短すぎる食事時間は避けるべきです。
脂肪減少と断食を破るもの
体重減少の目標においては、総カロリー収支が最も重要です。しかし、時間制限食を長期的に続けると、身体が脂肪をエネルギーとしてより多く利用するようになり、カロリー制限下での脂肪減少を促進する可能性があります。
「何をしたら断食が破られるか」には明確な答えがなく、文脈に大きく依存します。
- 水、ブラックコーヒー、お茶、カフェイン錠剤は断食を破りません。
- 砂糖(特に単純糖質)は、たとえ少量でも断食を破る可能性が高いです。
- 脂肪のみの摂取(MCTなど)は、空腹状態であれば断食を破らない可能性が高いですが、タンパク質は中間の影響を持ちます。
- 人工甘味料や植物由来の甘味料(ステビアなど)は、一般的に血糖値への影響は最小限であり、適度な量であれば断食を破るとは言えません。
実践的なツールと結論
時間制限食の実践には、「My Circadian Clock」ウェブサイトや「Zeroアプリ」などの無料リソースが役立ちます。
My Circadian Clock:https://www.mycircadianclock.org
最終的に、自分にとって最適な時間制限食スケジュールは、個人のライフスタイルや身体の反応、目標に大きく依存します。8時間の食事時間枠は、多くの研究で支持されており、健康効果と社会的適合性のバランスが良い基準となります。最も重要なのは、自分自身の身体のシステムを理解し、安全な実験を通じて最適な栄養スケジュールを見つけることです。「いつ食べるか」が「何を食べるか」と同じくらい重要であるという原則を忘れずに、健康管理に役立ててください。

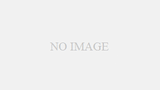
コメント